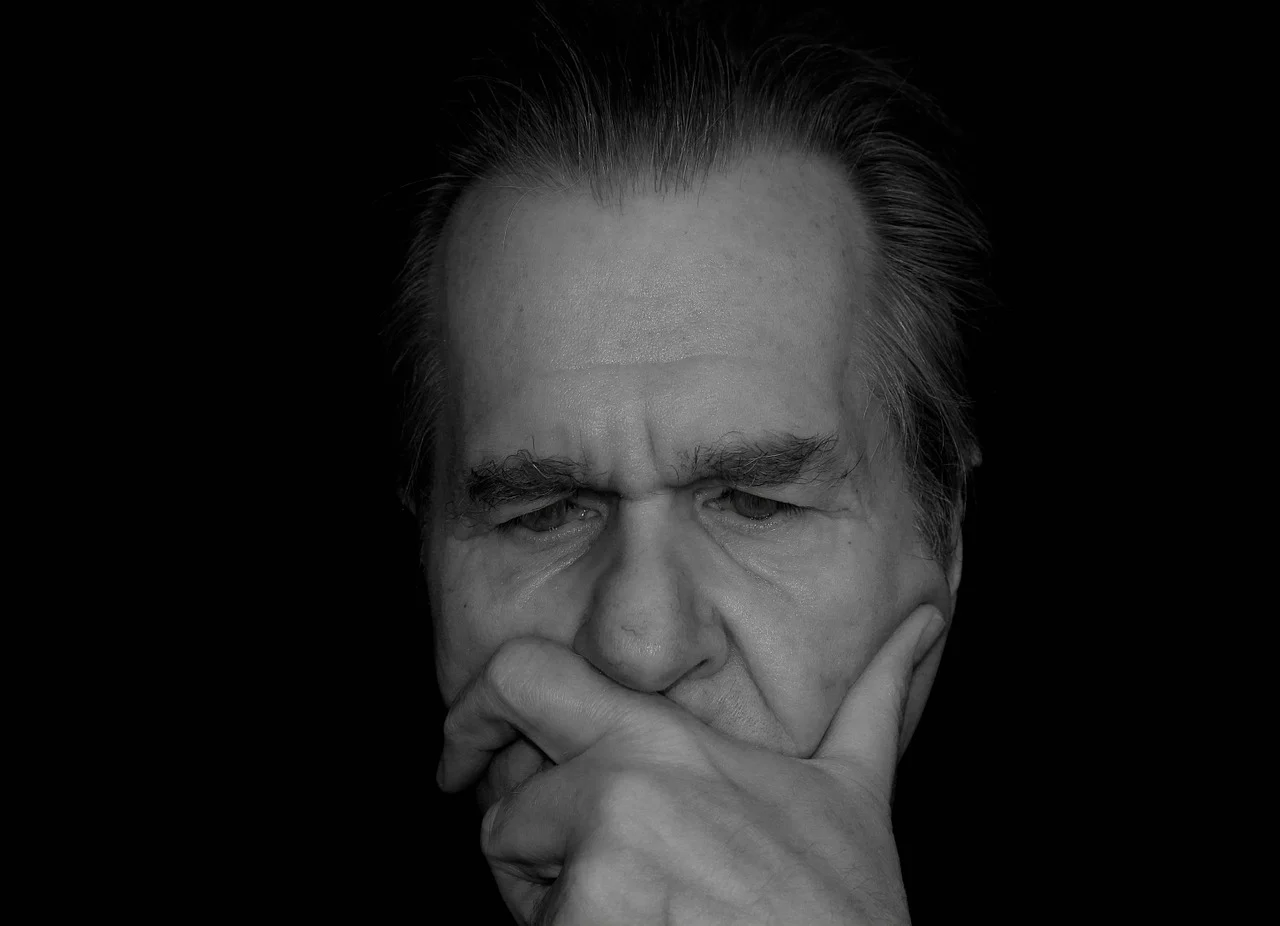今回は井上裕之さんが書かれた「人生を自由にしてくれる本当のお金の使い方」という本を解説します。
 | 新品価格 |
この方はこんなあなたにオススメです。「お金の不安を抱えている」「お金をどう使えば幸せになれるかを知りたい」そんな方におすすめの本です。
近年は少子高齢化、労働人口の減少、年金への不安、そしてコロナ下と暗い要素ばかりでお金の不安を抱えている人が増えています。しかし著者の周りにはお金の不安を抱えている人は見当たらないのだそう。
それはなぜかというと、「お金の稼ぎ方以上に使い方が上手だからだ」と著者はいいます。本書はその使い方について書かれた本です。
それではさっそく紹介していきます。
というわけでいつも通り最初にこの記事の結論を言っておきます。
結論:「お金は良い使い方をすると使った以上に入ってくる」「学び、社会貢献、体験にお金を使おう」
というわけで、この記事では「お金は循環させて増やしていく」「人生をより自由にしてくれるお金の使い方」「結果を出す人の共通点」という順番で解説していきますのでぜひお楽しみください。
お金は循環させて増やしていく
この章では「お金は循環させて増やす」というテーマについて本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは「お金は貯めるものではなく回すもの」「お金を自己成長と社会貢献に使う」という2つのポイントです。
ではそれぞれ掘り下げていきます。
お金は貯めるものではなく回すもの
1つ目のポイント「お金は貯めるものではなく回すもの」。
「金は天下の回りもの」ということわざをご存知でしょうか?このことわざはお金は一箇所に留まるものではなく、常に人から人へ回っているもの。今はお金を持っていてもいつか失うこともあるし、今お金を持っていなくてもいつかは手にすることもある、という意味です。
著者自身もこれと同じ考えで、お金は循環させた方がいいと考えています。お金を循環させることによって自分が成長する、人生のバランスが整う、社会貢献につながるなどのメリットが得られるからです。
もちろん循環させることがいいからといっても手元にまったく残さなくていいというわけではありません。万が一のリスクに備えて手取り月収の3ヶ月から6ヶ月程度は貯めておいた方が良いでしょう。
あくまでも貯蓄や節約を目的にはせず、お金を循環させることは意識すべきです。お金を貯め込むことに執着を持つ人の方が、一見するとお金をためるスピードが早くなり、経済的な自由に早く到達できそうだと思いますよね?
しかしそうではないと著者は言います。必要な時に必要なものにお金を投じることでお金は良い循環を生み、使った以上に入ってくるようになるというんです。
お金の循環には2つの意味があると著者は考えています。それは「社会を支える循環」と「エネルギーの循環」です。
社会を支える循環
まず1つは社会を支える循環です。お金は個人、企業、国、この3つの間で循環しています。私たちは労働の対価としてお客様や勤め先からお金を受けとっております。受け取ったお金で商品やサービスを購入します。
個人や企業は国に税金を納めます。税金によって行われる社会保障、補助金、公共サービスの提供を受けます。このような循環で成立しているということが見えてくると、日本の景気はなかなか上向かない原因の一つも見えてきます。
それは個人や企業がお金を使いたがらないことです。老後が心配だから、先行きが不透明だから頭金を溜め込むと、社会にお金が回らず悪循環に陥ります。個人や会社がお金を使うことで世の中をお金が循環し、景気が上向くわけです。
そして景気が上向けば給料が上がります。国も税収が増えます。社会保障も充実していくわけです。
エネルギーの循環
次にエネルギーの循環について。
エネルギーとはそのものが持っている潜在的な力のことです。そしてお金にもエネルギーがあるというのが著者の主張です。
またエネルギーには良いエネルギーと悪いエネルギーがあるとも著者は言っています。悪いエネルギーは悪い出来事を、いいエネルギーは良い出来事を引き寄せます。
類は友を呼ぶという言葉がまさにそれを表しているわけです。いいエネルギーは良い出来事を引き寄せるの例としては、人に優しくすると人から優しくされる、一生懸命努力をすると成果が出る、自己投資をするとスキルアップする。そしてさらにお金が稼げるようになるというようなことです。
笑顔な人、元気な人もそばにいるだけで元気をもらえるというのを体験したことがある人も多いと思います。こうした感情の電波もエネルギーの引き寄せの一例だといいます。
そしてお金にもいいエネルギーを呼ぶ使い方があるというわけです。その点については次の項目で説明します。
お金を自己成長と社会貢献に使う
というわけで続いて2つ目のポイント「お金を自己成長と社会貢献に使う」。
良いエネルギーを取り入れるにはお金を「自己成長」と「社会貢献」に使うことだと著者は言います。
自己成長と社会貢献にお金を使うと良いエネルギーを取り込めるので、お金の好循環につながります。自己成長のお金とは学びや経験に使うお金のこと、社会貢献のお金とは社会のため人のためや誰かの応援に使うお金のことです。
自己成長については次の章で具体的な中身を紹介します。自己成長でお金が入ってくるようになるというのはわかりやすいと思いますが、社会貢献の方は一見するとそうでない気もするでしょう。
しかし、「情けは人の為ならず」なんです。これは人に対して情けをかけておけば、巡り巡って自分にもいい報いが返ってくるという意味のことわざです。
実はこの「情けは人の為ならず」の正しさを確認した研究があります。大阪大学大学院人間科学研究科の研究グループの研究です。登場するのは3人の幼児です。幼児Aに幼児 Bが親切していたとします。この様子を見ていた幼児Cは幼児Aに対して選択的に親切にしていました。
つまり親切を行う幼児は後に周りの幼児から親切にしてもらいやすい、自分が親切にした分を回りの幼児から返してもらっているということです。
これは大人の社会でも同じです。社会のため、人のためにお金を使うと巡り巡って自分のところに返ってくる、これが著者の考えです。
人生をより自由にしてくれるお金の使い方
続いて「人生をより自由にしてくれるお金の使い方」。この章では人生をより自由にするお金の使い方というテーマについて、本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。
解説するのは「学びは確実なリターンが期待できる投資である」「体験にお金を使うと幸福度が長続きする」という2つのポイントです。
ではせそれぞれ掘り下げていきます。
学びは確実なリターンが期待できる投資である
1つ目のポイントを「学びは確実なリターンが期待できる投資である」
お金を循環させることが重要という話を前の章でしました。ではまず最初に何をすればいいのでしょうか?
その答えが自己成長に使うことです。
まずは学びにお金を使うことです。学びとは例えば資格の取得、語学習得、入学試験や人としての意識や生きていく姿勢を高めるもの、仕事に向かう意欲やモチベーションを磨くものといったものです。
著者が学びへの投資を進める理由は3つあります。「学びへの投資は損をしないこと」「視野が広がること」、そして「人間関係が広がること」この3つです。
順に掘り下げていきます。
学びへの投資は損をしないこと
まず1つ目「学びの投資は損をしない」
例えば不動産、株、家、車といったような資産は値段が変わってしまいます。リーマンショック、チャイナショック、コロナショックといったショックが起こると、こういった資産の価値は暴落し、大きな損失を抱えることになりかねません。
つまり不動産や株式への投資はリターンが不確実だということです。
その一方で学びはリターンが確約されています。学びの成果を確実に自分のものになります。経済的なショックなどで暴落することはありません。
著者の知る成功者の多くはこういうのだそう「今全てを失っても身一つでやり直す自信がある。5年くれたら今以上の成果を出す自信がある」
この自信の源泉が学びなんです。やり直せると言い切れるのは、専門知識だけでなくビジネス、成功哲学、自己啓発、科学、芸術、音楽など様々な自己投資で自分という資産を高め磨き上げた結果です。
著者自身お金に糸目をつけず学びへの投資を続けてきたそうですが、投資に見合う成果が出なかったことは一度もなかったと断言しています。
視野が広がること
では続いて二つ目の理由「視野が広がる」
著者が専門分野である歯科以外の勉強を始めたのは30代中盤だったそうです。一般教養も知らない専門バカでは一流になれない、人としての器を大きくしなければ一流になれないといったようなことに気付き、専門分野以外の学びをするようになったといいます。
その結果視野が広がり、今までの自分とは違った視点、他の人と違った視点で物事を考えられるようになったことで自分に付加価値をつけることができたといいます。
人間関係が広がる
最後に3つ目の理由は「人間関係が広がる」ことです。
セミナーに参加するとさまざまな人との交流が生まれます。講師やセミナーを主催するスタッフと知り合うこともあるわけです。著者自身学びに投資するようになってから、人間関係が広がったことで出版のチャンスを得ることができたことをはじめ、多くの収穫を得てきました。
セミナーでは講師はもちろん、セミナーのほかの参加者とのコミュニケーションを通しても新しい知見を得ることができるわけです。
というわけで以上が学びへの投資を進める3つの理由でした。
体験にお金を使うと幸福度が長続きする
では続いて2つ目のポイント「体験にお金を使うと幸福度が長続きする」
もう一つ学びと同じように一度身につけたらなくならないものがあります。それは経験です。
物やお花ではなくなっても、体験したことはなくなりません。体験は自分の中に残り、確実に積み上がる資産と言えます。また物にお金を使うよりも体験のためにお金を使った方が幸福度が高いということは研究でも分かっています。
ハーバード大学ビジネススクールの社会科学研究者マイケルノートン教授の研究によれば、ものを買った瞬間は幸福度が高くとも、その後すぐに幸福感を感じなくなってしまう。
なぜものの幸福度が下がってしまうのかといえば、それは慣れてしまうからで、持っていて当然と思うようになるからだというわけです。
体験はその場限りですがものはいつまでも手元に残ります。ですからものを買ったほうが幸福度では長続きすると私たちは思いがちです。
しかし実際は逆だということ。人生の豊かさはいくらお金を持っているかで決まるのではなく、何をしてきたのか、どんな体験をしてきたのかで決まると著者は言います。
お金の量より体験の量、貯めるべきは金融資産ではなく体験資産です。体験を通して感じたこと、学んだことこそその人を成長させる最良の資産になります。
結果を出す人の共通点
では続いて「結果を出す人の共通点」。この章では結果を出す人の共通点というテーマについて本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。
解説するのは「0か100かで考える」「人のせい環境のせいにしない」という2つのポイントです。
ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント「0か100かで考える」
著者は結果を出す人には5つの共通点があるといいます。
- 0か100かで考える
- 人の性環境のせいにしない
- 失敗やピンチもチャンスと考える
- 泥臭く誰よりも努力を続ける
- どこまでも高い目標を持つ
という5つの共通点です。
今回はこの中から一つ目の「0か100かで考える」、そして2つ目の「人のせい環境のせいにしない」この2つに絞って解説します。
0か100かで考える
まず1つ目「0か100かで考える」
0か100かという話をすると、「白か黒かで物事を考える人は思考が単調になる」「完璧主義は自分にも他人にも厳しくなってしまう」というような意見も出てくるかもしれません。
しかしここで言う0か100かというのは完璧主義を意図したものではありません。
著者の言う0か100かというのはどちらかに振り切った行動をするという意味です。
言い換えると結果を出したいのであれば、やると決めたことは手を抜かない、自分にとって価値のないことはやらないということです。
著者はお金も時間も、「本当に大切な事」「本当に価値のあること」に集中すべきだと述べています。
まず今自分がすべきことは何かを考えます。そしてすべきことが明確になったら全力を尽くす。余計なことを考えず、今できることをとことんやるということです。やるならやる、やらないならやらない。結果を出したいなら中途半端を止めて振り切ることが大切です。自分の力をすべて出すことだけを考えて行動すれば結果はおのずとついてくると著者は言います。
人のせい環境のせいにしない
では続いて2つ目のポイント「人のせい環境のせいにしない」本来人生のあらゆる結果はすべて自分の責任です。仮に環境的な問題から選択肢が狭かったり、他人に言われたことであったとしても、結局は環境や他人のせいではなく、そうすると決めた自分の責任なんです。
しかし、何かがうまくいかなかったときに「失敗したのは自分のせいではなく、まるまるのせいだ」というように誰かや何かに責任押し付ける人もいます。
これは誰かや何かに責任を押し付けておくことで自己評価を下げず、自分を守ることができるからです。
しかしこの時に2つのものを失ってしまっています。それは「成長機会」と「信頼です」。
失敗の原因が外にあるといういうことにすると、自分の選択、判断、行動の結果を検証する機会を失ってしまいます。これがすなわち成長機会を失うということです。
結果を出し続ける人は問題の原因を自分の行動や思考にあると考えます。そしてこのやり方が失敗した原因を分析しようとpdcaサイクルを回して改善していきます。だからこそ同じ失敗を繰り返さないようになります。
原因が外にあると思っていては次も同じ失敗を繰り返すでしょう。そして失敗を誰かや何かのせいにするとその一時だけはミスによる自分の損失を避けることができるでしょう。
しかし本当は自分に原因があったと発覚したとき、周囲の反感を買うことになります。もし仮にミスの原因が本当は自分にはなかったとしても、自分にできることは本当になかったのか、これを磨き直せる人は信頼されるでしょう。
周囲の信頼を得られる人は、失敗しない人ではなく、失敗を人のせいにしない人でしょう。
まとめ
お金は循環させて増やしていく。
ここでは2つのポイント「お金は貯めるものではなく回すもの」「お金を自己成長と社会貢献に使う」という2つのポイントについて解説しました。
人生をより自由にしてくれるお金の使い方。
ここでは2つのポイント「学びは確実なリターンが期待できる投資である」「体験にお金を使うと幸福度が長続きする」という2つのポイントについて解説しました。
結果を出す人の共通点。
ここでは2つのポイント「0か100かで考える」「人のせい環境のせいにしない」という2つのポイントについて解説しました。
今回紹介した本「人生を自由にしてくれる本当のお金の使い方」についてまだまだ紹介できていない部分が多いです。今回の記事でもっと幸福につながるお金の使い方について知りたいと思った方はぜひ本書を手にとって読んでみてください。
いつも通りリンクは下のに貼っています。
というわけで今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。
 | 新品価格 |